こんにちは、ひろです。
自筆証書遺言を作成するとき「縦書き」と「横書き」のどちらで書いたほうがいいのか?
たまに聞かれることがあります。
自筆証書遺言は、法律で定められた方法で作成しないと「無効」となることがあります。なので、縦書きにするか、横書きにするか、細かいことではありますが、それを気にするのはとても良いことだと思います。
今回は、自筆証書遺言についてです。
自筆証書遺言は「縦書き・横書き」どちらで作成してもOK!
結論を言ってしまうと、自筆証書遺言は縦書きで書いても、横書きで書いても、どちらで書いても問題はありません。
どちらも有効な遺言として扱われます。
法律上の規定もありませんし、判例もありませんので書きやすい方で作成しましょう。
仕事の関係で、顧客の遺言書を拝見することがありますが、縦書きの遺言、横書きの遺言どちらもあります。ちなみに、最近私が扱った遺言は「横書き」のものがほとんどです。
自筆証書遺言を作成してみる
この記事を読まれている方は、縦書きと横書きを悩まれていることから、まだ自筆証書遺言を書いたことがない方だと思います。
なので、下書きを作成する感じでもいいので、まずは遺言を作成してみましょう。実際に書いてみると、縦書きと横書きのどちらの方が書きやすいかも分かります。
自筆証書遺言の作成に関してはこちらの記事が参考になると思います。
≫【注意】自筆証書遺言が無効になる場合【必要事項・加除訂正・文章】
≫自筆証書遺言で使用する「用紙・筆記具・印鑑」に法律上の規定はあるのか?
ネットよりも「本」を参考に自筆証書遺言を作成する
先ほども言いましたが、自筆証書遺言は、法律で定められた方法で作成しないと「無効」となってしまう場合があります。
なので、作成にあたり、ある程度の法律知識が必要になります。
ネットでも分かりやすい質の高い情報が多いですが、ネットには間違った情報も多く存在するので、遺言の作成をネットの情報だけに頼るのはおすすめできません。
遺言は、相続人同士の争いを未然に防ぐなど、とても重要な役割があるものなので、無効とならないよう細心の注意を払って作成するべきです。
最近は、自筆証書遺言の作成方法の書籍も多く販売されていますので、本屋さんで分かりやすいと感じたものを一冊購入してみましょう。私も何冊か持っていますが、図や表をたくさん使い、とても分かりやすいものが多いです。
自筆証書遺言の作成を専門家に相談する
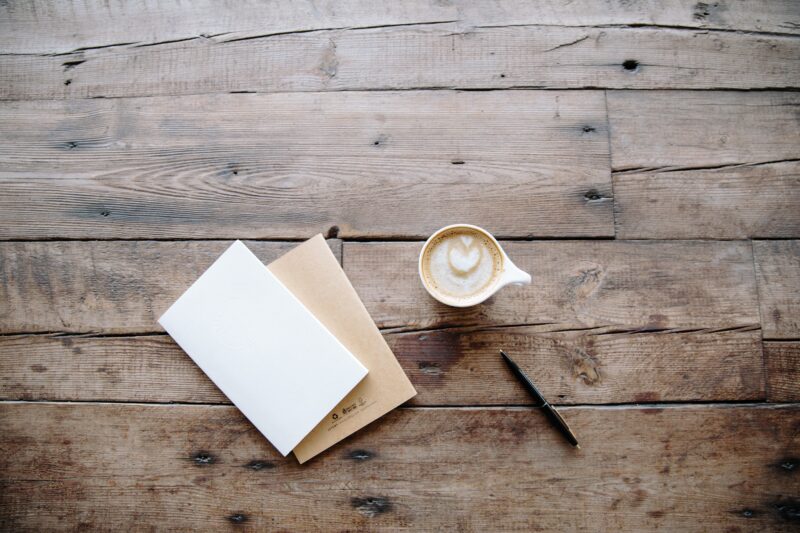
自分の作成した遺言が「有効なもの」として扱われるのか不安だという方は、専門家へ相談することをおすすめします。
自筆証書遺言作成の専門家としては、弁護士と行政書士がいます。基本的にどちらに相談しても同じ結果となりますが、費用は行政書士の方が安い場合が多いです。
注意点としては、相続を専門にしている弁護士や行政書士に相談しに行くことです。弁護士も行政書士も業務範囲が広く、専門としている分野はその先生によって違います。
新人かベテランかでも差がありますが、様々な業務を取り扱っている事務所より、相続を専門にしている先生のほうが知識や経験が豊富なのでおすすめです。
弁護士や行政書士に遺言作成を依頼する費用
下記の要因によって、費用に差がでます。
- どの専門家に依頼するか?
- どのくらいの財産があるか?
- 遺言の内容
一律の料金を設定している事務所もありますが、これらの事情によって料金が変わってくる事務所も多くあります。実際にかかる費用は、依頼前に信用できる専門家へ問い合わせしてみましょう。
自筆証書遺言より公正証書遺言がおすすめ
今回は、自筆証書遺言についての説明でしたが、遺言作成にあたっては自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうがおすすめです。
理由は公正証書遺言のほうが、トラブルになる可能性が低いからです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するので、自筆証書遺言のように有効性が問題となることがほとんどありません。費用はかかりますが、確実です。
自筆証書遺言を作成した場合でも、いずれどこかのタイミングで公正証書遺言にすることをおすすめします。


