今回は、行政書士業務で使える「分かりやすい文章の書き方」です。
行政書士は書類を作成することが多いので、当然、文章を書くことも多いです。
文章は、いかに相手に分かりやすく、こちらの意志を使えられるかが重要です。
どんな点を気を付ければ良いのか?
具体的に説明します。
行政書士業務で使える分かりやすい文章の書き方
文章は、簡潔、明瞭、シンプルに書くと分かりやすくなります。
具体的には、次の点に注意しましょう。
- 文を短く区切る
- わかりやすい言葉を使う
- 箇条書きを使う
順番に説明します。
文を短く区切る
文章は短く区切ることで、分かりやすく見やすくなります。
ついつい「~が」や「~で」という言葉を多用して文章を長くしてしまいがちですが、そういった文章が多いと、読みにくいうえ相手に内容が伝わりづらくなります。
また、句読点の位置に気を付けるのも大切です。
句読点には、句点(。)と読点(、)がありますが、あえて増やすことで見やすくなる場合もあります。
わかりやすい言葉を使う
できる限り「わかりやすい言葉」を使うのも大切です。
難しい言葉や漢字を使っても、相手に伝わらなければ意味がないですからね。
箇条書きを使う
箇条書きを使うと、文章は見やすくなります。
最初に箇条書きで書いて、順番に説明していくスタイルは便利です。
情報が整理されいるので理解もされやすくなります。
文章を書く練習をする
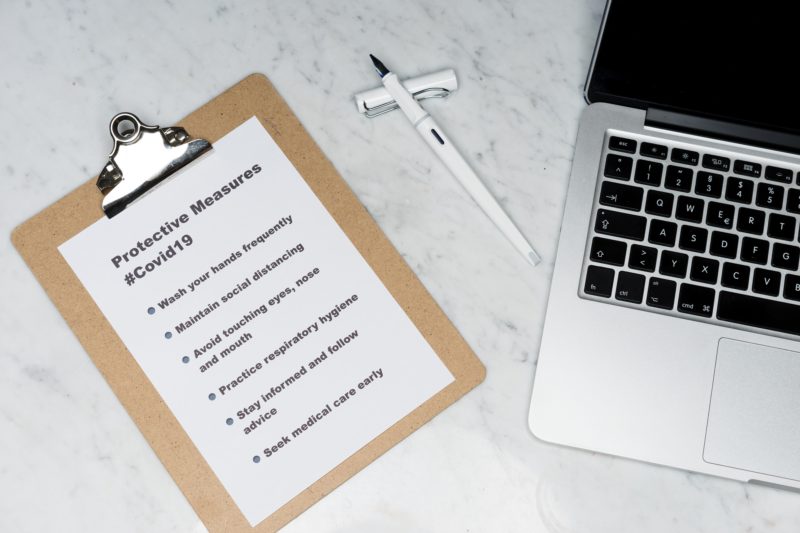
文章は書いた回数だけ上手くなります。
なので、何度も書いて練習することが大切です。
その練習に便利なのが「ブログ」です。
無料のブログもありますので、文章力を上げたい人におすすめです。
コツは、「とにかく書く」です。
最初から上手く書くことは考えないほうがいいです。
分かりやすい文章が必要な業務
何度も練習して、分かりやすい文章が書けるようになると、行政書士の業務でも、その能力を活かすことができます。
例えば「遺言書」の業務です。
遺言書は、ダラダラと長文を書くのではなくて、依頼者が望む内容を、法的にシンプルに分かりやすく書く必要がありますからね。文章力は重要です。
また、行政書士は郵送で顧客と書類のやり取りをすることがあります。
その場合も、分かりやすい文章が書ければ「不備」が減り、業務がはかどります。
今回はここまです。
読んでいただき、ありがとうございました。


